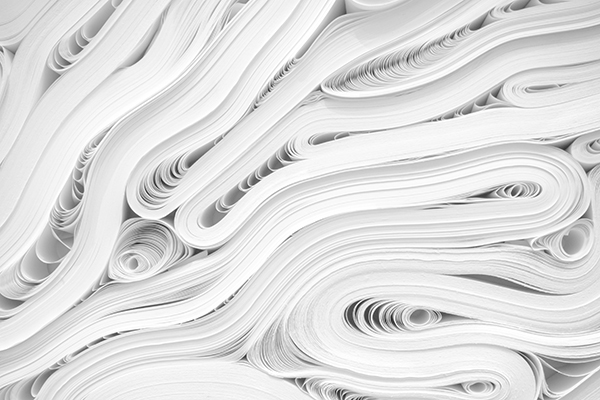
日々、「DX」という言葉が飛び交っています。
その進捗状況や組織の大小に関わらず、「当社もDXに取り組まないといけない」と、世相に逆らわずに漠然とある種の使命感を抱き、検討している組織も多いのではないでしょうか。しかし、自社がデジタル化に成功し、変革(=トランスフォーメーション)した先にはいったい何が待っているのかを、具体的にイメージしている組織はどのくらいあるのでしょう。
今回コラムで取り上げるのは、DXの入口と評される「ペーパーレス化」について。ペーパーレス化は、コロナ禍を契機に導入した企業も多い「テレワーク」とも非常に相性の良い取組みです。
テレワークに関する当社グループの調査結果では、その導入(※今後の導入予定を含む)は約57.4%。そのうち、コロナ禍をきっかけに「導入が促進された」「初導入した」企業は約80%に及びます(FORVALブルーレポート2022年度版)。
また、製紙業界の調査では、テレワークとペーパーレス化に関連する興味深い発表がありました。
「2020年以降、コロナ禍によってテレワーク導入が進みデジタル化が促進、ペーパーレス化が進んだ結果、2019 年まで堅調に推移していた情報用紙の需要が、主力のPPC(Plain Paper Copier)用紙を中心に前年比10.9%減、2021 年も前年比2.5%減と連続して減少した」(「2022 年 紙・板紙内需見通し報告(日本製紙連合会)」)
このように、なかなか進まなかったペーパーレス化が、コロナ禍の影響を受け進んできています。
一方、コロナ禍の報道のなかで、
- ・契約書・帳票類に捺印のために出社している
- ・業務フローの中に紙による申請・承認・押印のプロセスが含まれているので出社せざるをえない
など、紙文化の弊害が多くのメディアで報じられたのも記憶に新しいのではないでしょうか。
ペーパーレス化とは、
契約書、報告書や議事録などの紙書類を、ITやスキャニング技術などを駆使して電子情報で記録・保管することで、業務の効率化と紙資源の節約を図ること
と定義されており、そのような非効率を無くしていこうとする取り組み。とはいえ、ペーパーレス化がどうしても馴染まない業態や、一部の業務があるのも事実。できる場合とできない場合が存在するのも事実。漠然と取り組むのではなく、紙問題に正しく向き合って現状を整理、柔軟に検討・取捨選択していくことによって生産性を向上させるのが吉。
さらに、地球に優しい経営の実現を目指していきましょう。
目次
ペーパーレス化の歴史を紐解く
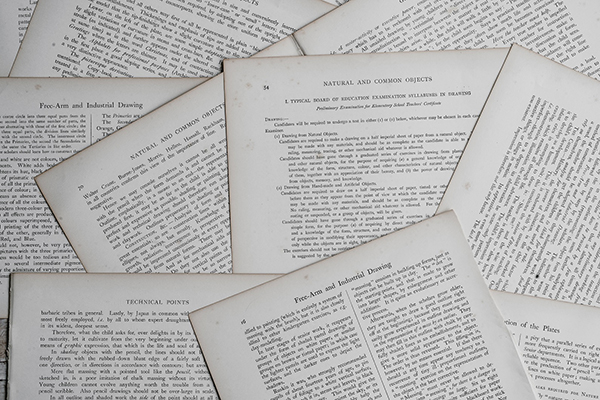
最初に「ペーパーレス化」という単語について、その歴史を紐解いてみましょう。
その起源は、1970 年代にまで遡ることに。当時提唱したのはOA機器メーカー各社でした。PC導入が少しずつ進んだ市場環境から将来見通しとして掲げられたのが「ペーパーレス」。その後、1990年代には、Windows95の登場、インターネット接続サービスの開始等によりPCの普及が劇的に進むなか、紙ではなくデータで授受する方法が大衆化し始めます。そして、紙の大量消費の問題が再燃しました。
しかし、さほど「ペーパーレス化」は進みませんでした。その要因は、
- 物理的要因 …社内のIT環境の未整備・IT人材の未確保、法整備の遅れ
- 情緒的要因 …根強く浸透した紙文化への依存
これらが挙げられています。
旧態依然として法制度下、書面で行なわなければならない業務が法律によって多数存在していたこともペーパーレスの推進の足かせでした。そこで、少しずつ法整備が進められました。
法整備の変遷
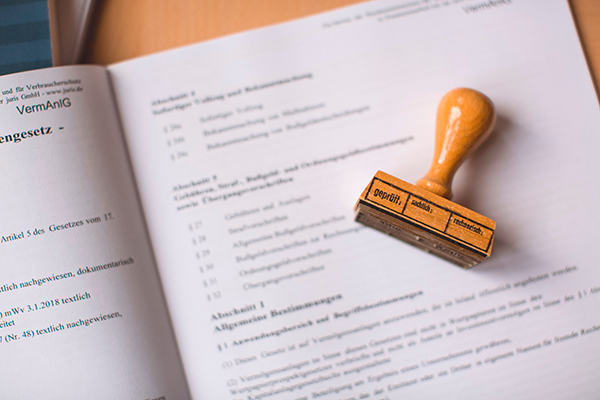
ペーパーレス関連の法案で最も関連深いのが、帳簿や領収書類等の電子的保存方法等を定めた電子帳簿保存法(以下「電帳法」)と呼ばれる法律です。
< ペーパーレス関連の法改正 >
1998年電帳法の施行
2001年電子署名法 (電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤)の施行
2005年電帳法の改正 (スキャナ保存制度の追加)
2015年電帳法の改正 (スキャナ保存制度の規制緩和、および契約書・領収証の金額上制限の撤廃)
2016年電帳法の改正 (スキャナ以外にデジカメ、スマホ等での撮影が可能に)
2020年電帳法の改正 (データ改編できないクラウドサービス等の利用可能に)
2021年電帳法の改正 (国税関係帳簿書類の電子化要件の緩和、電子取引の電子データ保存義務化)
電帳法の度重なる改正によって、ペーパーレスの阻害要因は少しずつ撤廃されていきました。近年では、ペーパーレス促進を阻む法的要因は低減しました。
しかし、2021年の改正に盛り込まれた「電子取引の電子データ保存義務化」は、2年の猶予期間が設定されてはいるものの、企業にとっては大きなシステムの改修や新規導入が必要な場合も少なくないため、新たな問題が噴出しています。
ペーパーレス化を進めるためには

ペーパーレス化は、単純に「紙を減らす」ことではありません。それはペーパーレス化の一部にすぎず、その本懐は、
無駄をなくして生産性を高める
ことです。「紙ありき」で運用されていた業務フローを見直すことで、生産性を高めていくことを狙ったもの。では、ペーパーレス化を実現すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。5つのポイントを整理しました。
ペーパーレス化のメリット
① 業務効率の向上
紙ベースで運用されていた帳票、稟議書などの業務フローを電子化(=システム化)することは、検索性を飛躍的に高めます。また、テレワーク実施時にもスムーズに情報を入手することができます。もちろん印鑑をもらうために出社する必要はなくなります。
② コスト圧縮効果
紙で印刷するためのコスト(複合機のカウンター料、紙代、カートリッジ代等)が大幅に削減できそうです。また、郵送による運用を電子化することでも費用が削減でき、さらに電子契約を導入すれば、収入印紙代を圧縮することも可能。印紙代は業種によってはインパクトのあるコスト削減効果が。
③ セキュリティ強化
紙の運用には、どうしても紛失や盗難のリスクが拭いきれません。電子化し、クラウド上に置かれたサーバーへのアクセス時やデータファイル開封時のパスワードロックを徹底することで、そんなリスクとは決別できます。
④ 省スペース化・スペースの有効活用
紙資料の電子化が済むと、それらの資料を格納していたキャビネット類に余裕が出てきます。まとまった面積を占める場合には、賃貸面積を縮小することができます。また、その面積を有効活用し、従業員のためのコミュニティスペースをつくったり、Web会議用のブースを導入することもできます。
⑤ 環境問題に貢献可
紙の使用量圧縮は、原材料のみならず、製造工程で発生する二酸化炭素を抑えることも大きな効果です。積極的に取り組む企業は周囲からの評価の高まりが期待でき、その結果、資金調達や採用面でも良い影響があるかもしれません。
さて、そんな多くのメリットが期待できるペーパーレス化ですが、どのように進めたらよいのでしょうか。
ペーパーレス化の手順・ポイントの整理

ペーパーレスの促進において「経営がその意義を理解し、自らが旗を振ってトップダウンで実践していくべし」と巷ではよく言われます。しかし、組織が大きくなればなるほど、実際それは困難。経営からの号令、意思表示は大切ですが、実感できるレベルで効果を出していく手順は、少し違います。
① 専門家の選定
社外の専門家を巻き込み伴走してもらいましょう。専門家によってカバーできる範囲、経験値や対応スピードが違いますので、慎重に検討します(「②」以降は専門家と一緒に行ないます)。
② スケジューリング
専門家と一緒に、ゴール設定と後工程の期日を設定していきます。ここで設定するスケジュールは開始時期に重点を置いたものです。後工程でペーパーレス化できる範囲が明確化されたり、導入するシステムによって差異が生じるため、早めに始動できるよう準備しましょう。
③ 現状把握
自社内で使用されてる紙の量はどの程度なのか、また、どのセクションでどのような用途で使用しているのか情報収集していきます。伝え方を間違えると社内の反発を招くことのあり注意が必要。社外の専門家から自社内に働きかけ促進してくれることもあるので相談しながら進めます。
④ 過去と未来の文書について対応方法を検討
既存の文書のペーパーレス化は、可能な場合とそうでない場合があります。熟慮せずに行なった場合に思わぬ落とし穴があることも。また、過去文書のペーパーレス化を行なう場合、同類の文書について未来の運用を漏れなく定めていくのも重要です。専門家の存在が必要な最大の理由がココです。また、通常業務を回しながら電子化を進めていくのも困難。専門家に委ねて推進しましょう。
⑤ ITツールの検討
文書管理、電子契約、クラウドストレージ、ワークフローなど、未来の運用に応じて導入するべきシステムを検討していきます。改正電帳法のような業務フローに大きく影響する法律は漏れなくチェックします。システムによっては、ベンダーが異なっていてもデータ連携させることができ、生産性をさらに高めてくれる優れものも。これらも専門家が活躍してくれるポイントです。
⑥ 優先順位付け・スケジューリング
ペーパーレス化する範囲、導入するシステムが決まったら、その優先順位を付け、ある程度正確なスケジュールを引いていきます。
⑦ ペーパーレス化開始
FRSのペーパーレス化支援サービス

ペーパーレス化には、以下の5つのメリットが期待できるとお伝えしました。
① 業務効率の向上
② コスト圧縮効果
③ セキュリティ強化
④ 省スペース化・スペースの有効活用
⑤ 環境問題に貢献可
FRSでは、自社の事業ドメインと、フォーバルグループのサービスラインナップを活かし、一気通貫でソリューション提供することができます。
業務効率の向上、コスト圧縮(上記の①、②)のコンサルティングについては、「PPLS(ププルス)」というソリューションメニューを、また、セキュリティ対策や省スペース化等(上記の③、④)については、FRSのネットワークソリューションやオフィスコンサルティングサービスをご用意しています。
PPLS(ププルス)について
PPLS(ププルス)は、電子化、データ入力等を通じた業務改善コンサルティングサービス。ペーパーレス化を進めるにあたって直面する課題や様々な障壁を、ペーパーレス化の経験豊富なDXアドバイザーがお客様に伴走しながら推進していきます。
さいきんの事例をひとつご紹介します。
マックス株式会社様(東証プライム上場)
創 業:1942年
従業員数:2,493人(連結)
事業内容:産業機器、オフィス機器、HCR機器の製造・販売
■文書データ化に取り組んだ背景
全部門がビル内で引っ越しをすることになり、不要書類の整理が必要になりました。書類整理を進めていくうえで、各種帳票や商品仕様書などの保管ルールが定められた書類などは処分できないため、電子化が急務となりました。
■外部委託を考えた理由
自部門でスキャンデータの作成が困難だと判断したため。
(1)複合機は他の部門と共有利用
(2)スキャンする作業の時間が取れないこと
(3)保管されている書類のボリュームが多かった
■PPLS(ププルス)選んだ理由
以前から他の部署ではデータ入力やスキャンデータ作成を依頼していた実績があり、仕事も丁寧だったので勧められ、見積金額もリーズナブルで採用を決めました。思っていたよりも早く納品されて出来栄えも良く、丁寧に仕上がっていました。
■サービスを利用した感想
全部門のビル内での引っ越しを機に、不要な書類を処分することによって新たなスペースを確保するといった課題を解決できました。自分の業務に支障をきたさず、短期間でデータ化することができました。専門家に依頼したため、慣れない仕事による作業ミスを回避することができ、ストレスを感じずに済みました。
このようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひPPLS(ププルス)をご検討ください。
さいごに

今回は、ペーパーレス化についてご紹介してきました。
DXやテレワーク、ペーパーレス化について悶々とお悩みの組織のかたは多いと思います。まずは私たちなど、専門家にお声掛けいただき、具体的なイメージを持っていただけたらと思います。もちろんご相談は無料で承ります。
最後までお読みいただきありがとうございました!
(著:FRS広報チーム)